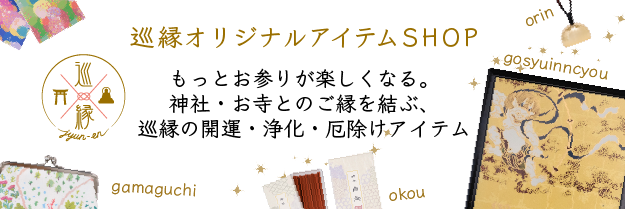お知らせ
NEWS
関東担当ライターRyoが、日帰りで伊勢神宮に行ってきました。
2024年の夏にいただいた”年パ...続きを読む
2月3日は節分、そして本日の4日は九星気学での1年がはじまる日です。
今回は2月の運勢と、それ...続きを読む
福島のおへそ郡山、鳥居が田んぼに連なる映え映えの光景があるらしい。
そこは...続きを読む
今年はどんなお祭りに行きますか?
午年の今年、巡縁がお勧めしたいのは「相馬野馬追」祭り。
...続きを読む
 基本情報
基本情報
- 名称
- 勝尾寺
- 読み方
- かつおうじ
- 別称
- だるま寺
- 所在地
- 〒562-0021
大阪府箕面市粟生間谷2914-1
- 参拝時間
- 平日 8:00〜17:00/土 8:00〜17:30/日祝 8:00〜18:00
- 参拝所要時間
- 約120分
- 参拝料
- 大人400円、小中学生300円、未就学児100円、2歳以下無料
- 御朱印
- あり
- 御朱印帳
- あり
- 電話番号
072-721-7010
- FAX
- アクセス
- 阪急電鉄「箕面駅」から15分(Osaka Metro御堂筋線「千里中央駅」下車、阪急バス「北摂霊宛」行「勝尾寺」下車すぐ) 名神高速道路「茨木インター」より国道171号線経由、「清水」交差点右折(約15分)
近畿自動車道・中国自動車道・名神高速道路「吹田インター」より中央環状線・国道423号線経由、「白島」交差点右折、「栗生外院」交 差点左折(約10分)
中国自動車道「池田インター」より中央環状線・国道423号線経由、「白島」交差点右折、「栗生外院」交差点左折(約10分)
- SNS
 詳細情報
詳細情報
- 御本尊
- 十一面千手観音
- 山号
- 応頂山
- 宗旨・宗派
- 高野山真言宗
- 創建時代
- 神亀4年(727)
- 寺格
- 開山・開基
- 善仲・善算
- 札所など
-
西国三十三箇所霊場第23番札所
法然上人二十五霊場第6番札所(二階堂)
摂津国八十八ケ所第54番札所
摂津国33箇所第22番札所
神仏霊場巡礼の道第65番(大阪24番)
- 文化財
- ご由緒
-
伝承によれば、勝尾寺の草創経緯は次のとおりである。神亀4年(727年)、 藤原致房の子の善仲、善算の兄弟はこの地に草庵を築き、仏道修行に励んでいた。それから約40年後の天平神護元年(765年)、光仁天皇の皇子(桓武天皇の異母兄)である開成が2人に師事して仏門に入った。宝亀8年(777年)、開成は念願であった大般若経600巻の書写を終え、勝尾寺の前身である弥勒寺を創建した。そして、数年後の宝亀11年(780年)、妙観が本尊の十一面千手観世音菩薩立像を制作したと伝えられる。
開成の僧としての事績については正史に記載がなく不明な点も多いが、北摂地域の山間部には当寺以外にも高槻市の神峯山寺など、開成の開基または中興とされる寺院が点在している。
勝尾寺は平安時代以降、山岳信仰の拠点として栄え、天皇など貴人の参詣も多かった。元慶4年(880年)、当時の住職行巡が清和天皇の病気平癒の祈祷を行い、「勝王寺」の寺号を賜るが、「王に勝つ」という意味の寺号は畏れ多いとして勝尾寺に差し控えたという。『日本三代実録』は、元慶4年、清和天皇死去についての記事で、同天皇が「勝尾山」に参詣したことを述べており、これが勝尾寺の文献上の初見である。
元暦元年(1184年)、治承・寿永の乱(源平合戦)の一ノ谷の戦いのあおりで焼失。文治4年(1188年)、源頼朝の命により、熊谷直実・梶原景時によって再建された。
承元4年(1210年)には晩年の、讃岐国流罪から戻った法然が当寺に滞在している。 出典・引用 https://hotokami.jp/area/osaka/Hmatp/Hmatpty/Dkktrz/8969/ ホトカミ
- ご利益
- 体験