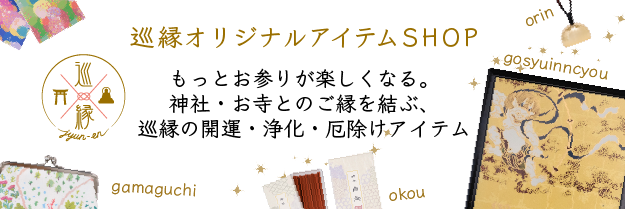お知らせ
NEWS
【キツネと油揚げ】初午と稲荷神社の深〜い関係|知れば知るほどおもしろい、商売繁盛と五穀豊穣を願う日本...続きを読む
小正月の15日もすぎてしまいました、お正月が終わって少し寂しいのは私だけでしょうか。
&nbs...続きを読む
前回に引き続き「元伊勢」のご紹介です。
眞名井神社は縄文時代の祭祀の跡が見...続きを読む
関西担当ライターRyoさんが言ってきたのは、
パワスポ大好き界隈でも有名な「元伊勢・籠神社(こ...続きを読む
 基本情報
基本情報
- 名称
- 戒壇院
- 読み方
- かいだんいん
- 別称
- 筑紫戒壇院 西戒壇
- 所在地
- 〒818-0101
福岡県太宰府市観世音寺5-7-10
- 参拝時間
-
- 参拝所要時間
- 約15分
- 参拝料
- 無料
- 御朱印
- あり
- 御朱印帳
- なし
- 電話番号
092-922-4559
- FAX
- ホームページ
- https://kaidanin.or.jp/
- アクセス
- 九州自動車道
「太宰府I.C」から福岡南バイパス経由 約4.5Km(約7分)
・国道3号/太宰府/筑紫野/九州国立博物館 の標識に従って 福岡南バイパス/国道3号 に入る
・右側 2 車線を使用して斜め右方向に曲がり、そのまま 福岡南バイパス/国道3号 を進む
・都府楼橋(交差点) を左折して 都府楼橋/県道581号 に入る
・右折して政庁通り/県道76号に入る
・観世大橋通り交差点を左折し、駐車場に入る
電車でお越しのお客様
西鉄福岡(天神)駅からお越しの方
西鉄福岡(天神)駅
| 西鉄大牟田線(特急・急行)約15分
西鉄二日市駅
| 西鉄 太宰府線 約2分
西鉄五条駅
徒歩約15分
- SNS
 詳細情報
詳細情報
- 御本尊
- 毘蘆舎那仏
- 山号
- 宗旨・宗派
- 臨済宗妙心寺派
- 創建時代
- 天平宝字5年(761)
- 寺格
- 開山・開基
- 鑑真、聖武天皇(勅願)
- 札所など
- 筑紫四国八十八カ所霊場第1番札所
- 文化財
- 木造盧舎那仏坐像(重要文化財)
- ご由緒
-
筑紫戒壇院は天下三戒壇の一つとして、大和の東大寺、下野の薬師寺の戒壇とともに知られています。東大寺に戒壇が設けられ聖武上皇を始め孝謙天皇や貴族等約400人が授戒したのは、鑑真和上が日本へ到着した翌年、天平勝宝6年(754)でした。
筑紫野の戒壇は天平宝字5年(761)聖武上皇勅願によって、観世音寺境内の南西の一角に設置され、九州の僧尼達の登壇授戒の道場として継承されて来ました。しかしながら戒壇創設の頃から、17世紀後半までの歴史はあまり確かではありません。東大寺の戒壇は十師が置かれ、東西の戒壇は五師でした。筑紫戒壇は西戒壇とも言われました。
近世の復興は寛文9年(1669)戒壇院の本尊毘廬舎那仏の修復に始まり、本堂の再建、修改築が行われました。その間に涅槃図の寄附(天和3年1683)、脇仏(文殊菩薩、弥勒菩薩 元禄13年1700)の新造、開山鑑真和上像の造立(宝永2年1705)、又鐘楼と梵鐘(元禄14年1701)が造られ筑紫野に梵鐘の音が響き渡りました。
元禄16年(1703)福岡藩三代藩主黒田光之の藩命によって博多禅宗、四ヶ寺(聖福寺、崇福寺、承天寺、妙楽寺)の管理下に置かれ、観世音寺から独立しました。明治6年(1873)臨済宗妙心寺派、博多 聖福寺の末寺となりました。
明治37年(1904)聖武天皇と鑑真和上の1150年諱法要が戒壇院近世中興東瀛老師(聖福寺128世)によって行われ、大授戒会も行われた。昭和36年(1961)開創1200年遠忌を真応和尚によって行われ庫裏等修改築されました。
平成3年(1991)台風により、本堂、庫裡に甚大な被害を被りましたが、平成6年復興されました。
出典・引用 https://kaidanin.or.jp/about/ 戒壇院ホームページ
- ご利益
- 体験
-
座禅会(毎月第1、3、5日曜日の午前8時~10時過ぎ
尚、坐禅を初めてされる方は坐禅の心得、座り方等の指導を行いますので開始30分前までにお越しください。
参加1回毎に500円、但し初めて参加の方は初回1000円。以後参加1回毎500円)
写経会(毎月第二、第四日曜日の午前8時より開始)