
2025.02.08
2021年、コロナ禍真っ只中の時期のことでした。緊急事態宣言が何度も出て、世間は完全に自粛モード。旅好きの私の心は、ささくれ立っていました。
同時期、職場の同僚がコロナ禍のダメージに加えて大切な人を亡くしたりして、精神をかなりやられていました。
そんな時に思いついたのが、巡礼です。
「そうだ、お寺に行こう!」
当時、外出こそ自粛モードでありましたが、神社仏閣巡りは屋外活動の一環として許容ムード。御朱印集めも人気でした。何より、気持ちが落ちている時こそ頼りたいのがお寺。月に1回、複数回かけて、基本は車を使って、日帰りで。そんな風に始めた旅でしたが、結果的には誰に話しても「えー!?」と驚かれる、なかなかの珍道中でした。
今回からは、そんな女子旅のご様子を、我々が回ったルートや時間、お金のことやグルメ情報なども交えて全10回ほどでご紹介したいと思います。コロナ禍という特殊な時期で、まだ巡縁ができていない頃のことですが、これから坂東三十三観音霊場巡りに挑戦してみたい方の参考になれば幸いです。
坂東三十三観音霊場とは、関東7都県に点在する観音菩薩を安置した三十三の霊場寺院のこと。
その歴史は、鎌倉時代初期にさかのぼります。当時、源平合戦で疲弊した人々は、死者の供養や恒久の平和を願っていました。そこで観音菩薩を篤く信仰していた源頼朝が、西国三十三観音霊場を真似た観音霊場巡りを開設。その後、秩父三十四霊場を加えて、現在でも多くの巡礼者が訪れる百霊場の一部となりました。
霊場巡りの際、最初のお寺に参拝することを「発願(ほつがん)」、最後のお寺に参拝することを「結願(けちがん)」または「満願(まんがん)」といいます。この名が示す通り、願いを決めてすべての霊場を参拝すれば、その願いが叶うと言われています。私は亡くなった親族の供養を、同行者は今後の人生の平穏と安定を願って巡りました。
三十三ヶ所ある札所は、回る順も手段も日数も自由です。続けて順番通りに巡るのはもちろん、複数回に分けて日帰りや1泊・2泊程度で巡る人も少なくありません。最低1番と最後の33番だけ守るのがおすすめですが、あとは回りやすい順番で行ってOKです。
四国八十八か所を巡る人は、多くが白衣などを着て、なかなか「ガチ」な恰好をしています。しかし、坂東三十三観音霊場は、都心にあるお寺なども巡るため、カジュアルな恰好の方が大半です。ただし、あくまでも旅行ではなく「巡礼」。服装や持っていくものなど、一定のマナーを守ることが大切です。
服装は結構自由で大丈夫ですが、破れたジーパンや露出の高すぎる服、サンダルなどを避けましょう。ちなみに、公式では「輪袈裟とお数珠だけは最低限」と推奨しています。
お数珠は、ご自身がお持ちのものを持参してください。法要で使うものでもいいですが、簡易的なブレスレットタイプが便利です。輪袈裟は持っている方は少ないでしょうから、通販などで用意しておくか、最初に訪れたお寺で授与していただくと良いでしょう。私たちは、以前お寺でいただいた絡子(らくす:お坊さんの簡易袈裟)とブレスタイプのお数珠を持参しました。なお、長く歩くお寺や階段も多いので、靴はスニーカーなど歩きやすいものをおすすめします。
「本当か!?」と思う価格でご提供できちゃった!福生社長の本当にオススメの一品。京都製のしっかりとした品質で、安っぽくないのにお手頃価格。
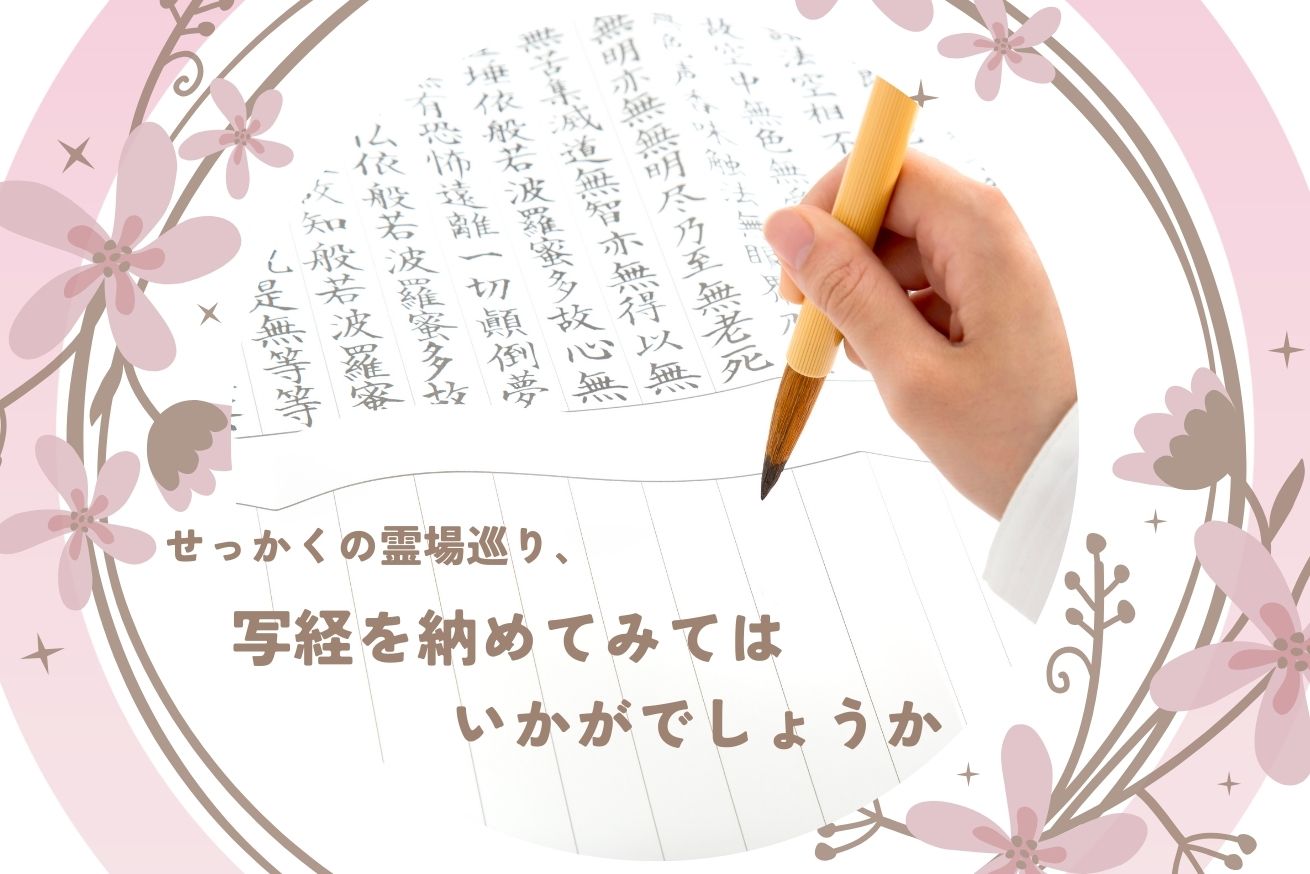
せっかくの坂東三十三観音霊場を巡る旅。記録を1冊にまとめるように、巡礼専用の御朱印帳を持っての参拝がおすすめです。御朱印帳は公式のものもありますが、私は何かの記念品でいただいた、大判の御朱印長を持参しました。思い入れのある御朱印帳で巡れば、思いもより深くなるもの。もちろん、巡縁で販売しているカワイイ御朱印帳を持って行くのもOKです。
そして、これも推奨なのですが、御朱印は本来、お寺に納経した印としていただいていたもの。なかなかできない巡礼をするのだから、写経を納めてみてはいかがでしょうか。
今回私は、すべてのお寺に般若心経の写経を納めました。もちろん、書くのは結構大変でしたが、参拝後の充実感が違います♪時間がないけれど納経に挑戦してみたい方は、「延命十句観音経」の写経でもいいと思います。たった42文字の短いお経なので、般若心経よりは挑戦しやすいですよ。
現代は小銭を使う機会が少ないので、あらかじめ巡礼用のお賽銭を用意しておくと安心です。私は日ごろから、お財布に小銭ができると、お賽銭用の貯金箱に入れるようにしていました。
また、御朱印代が毎回かかるので、こちらも別途用意しておくと便利です。出発する時に、その日訪れる霊場の分だけ、お賽銭と御朱印代をコインケースに入れておくのがおすすめです。
各札所では、献灯といってろうそくを灯し、そのろうそくでつけた線香を供えるところがあります。私は親族の供養の巡礼だったので、線香だけ自分の気に入ったものを持参しました。お寺によっては指定のものだけしか使えないところもあるので、指示に従ってくださいね。
また、納札は、寺院参拝をした印として自分の名前と住所を書いて納める札のこと。表面には自分の住所や名前・参拝した日などを、裏面に今回の巡礼の目的や願い事を書きます。50枚つづりで頒布されているので、1ヶ寺につき1枚、納札に入れていきましょう。
前置きが長くなりましたが、いよいよ1回目の旅の紹介です。
2021年1月、まだまだ寒い日に、巡礼は鎌倉からスタートしました。
車で向かったのは、第一番札所の杉本寺。以前はとにかく駐車場がわかりにくい上に細い坂を上って狭い場所に停めていたのですが、鎌倉側から朝比奈寄りに少し進んだ場所に有料駐車場ができていて、ハードルが下がっていました。都内から来る人は朝比奈方面から来ると思いますが、お寺より手前の右手に駐車場があるので注意して走行してください。

杉本寺は、鎌倉にある天台宗の古刹。鎌倉最古の寺と伝えられていて、天平時代、東国を巡っていた行基によって開かれたと言われています。平安時代に慈覚大師が自らの手で刻んだという十一面観音菩薩を本尊とし、鎌倉時代には源頼朝が御前立の観音像を寄進しました。
長い歴史を感じられるような、苔むした階段が有名なお寺です。残念ながら、現在はその階段は老朽化のため上ることはできず、横にある比較的新しい階段を上がっていきます。
一番札所にふさわしく、かなり雰囲気のある寺院です。本殿には巡礼に必要なものもたくさん頒布されているので、何も持っていない方はぜひこちらでそろえてください。前述の苔むした階段や、運慶作の像など、境内には見どころもたくさん。趣のあるお寺なのですが、駅から離れているからか観光客も少なく、静かでとてもステキな場所です。
御朱印は、本堂の中でいただけます。女性の住職さんで、とても美しい御朱印をいただきました。
無事に参拝を終えて階段を下りていると、タイワンリスが飛び跳ねていました。害獣と言われていますが、見た目はめっちゃかわいいんですよね♡まるでこれからの旅路を応援してくれているかのようで、いいことありそうだね、と、次の札所へ向かいました。
杉本寺を後にしたら、いったん鎌倉を出て、逗子市へ入ります。横須賀線の線路を渡り、細い住宅地の道を進んでいきます。突き当たった先には、岩殿寺への階段。すぐ手前にある無料の駐車場に停めて、参拝に向かいます。

岩殿寺は、逗子にある曹洞宗の寺院。杉本寺と同様、天平時代に行基によって開かれたと言われています。ご本尊は、通称・岩殿観音と呼ばれる十一面観音。吾妻鏡には、源実朝がしばしば参詣したと記されているそうです。
ここの特徴は、とにかく階段を上がる!ということ。2番目の寺院にして、軽い登山レベルの参拝となり、運動不足を痛感するハメになりました。
階段を上がるということは、景色がよくなる、ということ。本堂がある場所は、逗子の町を見下ろす絶景です。美しい景色を見ながらのお参り、まさにがんばって上がったご褒美ですね。
参拝を終えたら、階段下にある社務所で御朱印をいただきます。とても気さくな住職さんで、たくさんお話をしていただき、参考にしてねと巡礼の小冊子までいただきました。ありがたいですね。
車は再び、鎌倉へ。次は、鎌倉駅方面に戻っている途中にある、安養院です。お寺のすぐ横に駐車場があるのですが、残念ながらこの日は使用できず。近くにコインパーキングがたくさんあるので、そちらに停めました。

安養院は、鎌倉にある浄土宗の寺院。
実はとても複雑なお寺で、長楽寺・善導寺・田代寺という3つの寺院が関係しているそうです。
長楽寺は北条政子が、夫である源頼朝を弔うために長谷の近くに開山した寺院でしたが、兵火によって焼失。元々この地にあった善導寺と統一され、北条政子の法名を取って安養院長楽寺となりました。その後、江戸時代に妙本寺近くにあった田代寺が統合され安養院となりましたが、ご本尊の千手観音が田代寺にあったものであるため、現在でも田代観音と呼ばれているそうです。
ちなみに、いただいた御朱印にも「田代寺」と書かれていました。境内にはつつじがたくさん植えられていて、つつじ寺とも呼ばれているそう。さすがにまだ枯れ木でしたが、以前初夏に訪れた時は、もりっもりのツツジがそれは見事でした。
本堂に入ると、よく資料などで出てくる政子の像がお出迎え。境内裏手には政子のお墓と伝えられている場所もあり、まさに政子のお寺です。
本堂の前には鎌倉市の天然記念物に指定されている樹齢700年の巨大な槙の木があって、ツツジに負けずこちらもびっくりの大きさ。あまり広くはないですが、見どころがたくさんありました。
実は私は何度か訪れているのですが、つつじのシーズン以外は静かなお寺だったのです。が、この日は修学旅行の中学生が多く訪れていて、なかなかにぎやかでした。男女のグループで、男の子はただの石に上がったり下りたりして遊んでいる中、女の子はマジメに境内を散策していて、「ああ、いつの時代も同じ…」と、ほのぼのしてしまいました。
安養院の後で軽くお昼を済ませ、続いては長谷寺へ。言わずとしれた鎌倉の観光名所。長谷寺の入口にある交差点、一見T字路に見えるのですが、きちんと道があります。その路地を長谷寺方面に入れば、有料駐車場があります。人も多く、向かいから車がきてなかなかハードな駐車場ですが、勇気を出して突っ込んでください。

長谷寺は、鎌倉にある浄土宗系単立の寺院。
創建は奈良時代とも言われています。長谷寺と言えば奈良の長谷寺を思い浮かべる方も多いでしょうが、実はその長谷寺の開基である徳道が開いたお寺なので、同じ名前だそう。見どころは何と言っても、日本最大級と言われる十一面観音!徳道が大和の山中から採取した楠から二体の十一面観音を造り、一体を奈良の長谷寺に安置。そして、もう一体を祈請した上で海に流したところ、15年後に三浦半島に流れ着いたため、長谷寺に安置した、という伝説が残っています。実際にあの観音さんが「どんぶらこ」と海を流れていたら、ものすごい光景ですよね…
長谷寺といえば、鎌倉でもかなりメジャーな寺院。紫陽花や紅葉が楽しめるお寺としても有名で、私自身も何度も訪れていますが、いつ来ても大勢の参拝客がいる、とても華やかなお寺という印象です。
見どころはたくさんありますが、何といっても観音堂の観音様はいつ拝見してもその大きさに驚きます。日本最大級で、その大きさは何と9m以上もうあるそう!ありがたいと思う反面、日ごろの行いが悪い私などは、毎度ドキドキしてしまいます。
いきなり順番が飛ぶのですが、鎌倉から東京へ帰る途中なので、最後に横浜市にある弘明寺へ。鎌倉エリアからだと、鎌倉街道を進めば1時間ほどで到着します。住宅地を抜け、商店街を少しだけ通り、山門の右手にある弘明寺坂を上ったところに駐車場があります。駅がすごく近いので、歩行者が多いです、安全運転で向かってください。

弘明寺は、横浜市南区にある高野山真言宗の寺院。その歴史は古く、天平時代の聖武天皇の時代に建てられたと言われる、横浜最古の寺院です。本尊の十一面観世音菩薩立像は、天下泰平の願いを込めて一刀三礼(一刀刻む毎に三度礼拝するそう!)で掘られたそうで、現在は国指定の重要文化財に指定されています。
元々は「求明寺」と呼ばれていましたが、観音経偈文の中にある「弘誓深如海」という一文から一文字を取って、弘明寺となったそう。空海が訪れたと伝えられる由緒あるお寺でしたが、明治時代の仏教弾圧で一度は無住職になり、住職系図までもが紛失してしまったそう。しかし、明治後期に新住職が就任すると、地域住民の手によって弘明寺保勝会が設立され、見事に復興。山門前ににぎやかな商店街が並び、今なお地域住民が誇る寺院となっています。
弘明寺も何度か参拝に訪れたことがあるのですが、このお寺はいつ行っても地域の方がいらっしゃるという印象です。この日も、参拝中に息を切らせながら、地元の方らしきおじいちゃまが階段を上がって、参拝をしていました。山門前にある商店街がまたローカルな感じで、とてもステキ。地域に愛されているな~と感じるのです。
しかし、階段を苦労して上がっている方を見ると、少し罪悪感が…実はこのお寺、最寄りが京急と横浜市営地下鉄なのですが、地下鉄側からだと微妙な長さの階段を上がらなければならないのです!しかし、京急側からだと、この階段がスルーできてしまいます。そして、駐車場は、京急のすぐそばっ。さらに言えば、正面は絶対に、階段側なのです!我々は階段をスルーしている…いいのでしょうか?と、罪悪感を覚えつつ、階段を見下ろして、「ま、いいか」と参拝してしました…十一面観音さん、お許しください。
というところで、今回の巡礼は終了となりました。初回からかなり充実した内容となりました。
参拝の途中、鎌倉山の中にあるカフェ「ル・ミリュウ」に立ち寄りました。こちらは、東京の紀尾井町にある「ラ・プレシューズ」と同じ系列のお店で、モンブランが絶品のお店。高台にあるため、テラス席から鎌倉の山並みが一望できます。
この日も、オーダーしたのはもちろんモンブラン!和栗をたっぷり使った生絞りのペーストに、甘さ控えめのシャンティ―クリーム、そしてサックサクのメレンゲの組み合わせが最高なのです。
早速一口、いたただきます!と、手に取った瞬間でした。
ばさばさっ!

私の目の前に、黒い塊が飛んできて、あっという間にケーキが持ち去られてしまったのです!!
影の正体は…とんびでした!鎌倉では被害者が続出とは聞いていましたが、まさか鎌倉山の中で、しかもモンブランが狙われるとは!!!
驚きとショックでしばらくは茫然としていましたが、その後は笑いが止まりませんでした。
今回の巡礼で、私たちが使ったお金の記録です。
小計 4,290円
昼食:魚屋路で海鮮丼ランチ 1人1,276円
(本編で触れなかったのですが、チェーン店の回転寿司屋さんです。鎌倉ではめずらしく駐車場無料!)
お茶:ルミリュウでケーキセット 1,430円
小計 2,706円
レンタカー:4,835円
ガソリン代:1,304円
高速道路(都内から):3,010円
小計 9149円→1人4,575円
1人あたり、11,571円でした。
なお、2021年1月時での金額なので、増減がある可能性があります。あくまで、参考程度にとどめてくださいね。

毎回、様々な珍事件が起こった坂東三十三観音霊場巡り。第一回目を終えて…長い!
次からは、冒頭がなくなりますので、末永くお付き合いいただければと思います。
次回もまだ、神奈川県です。やはり、鎌倉時代に作られたものなので、鎌倉周辺が多いのですね。ぜひぜひお楽しみにお待ちください!
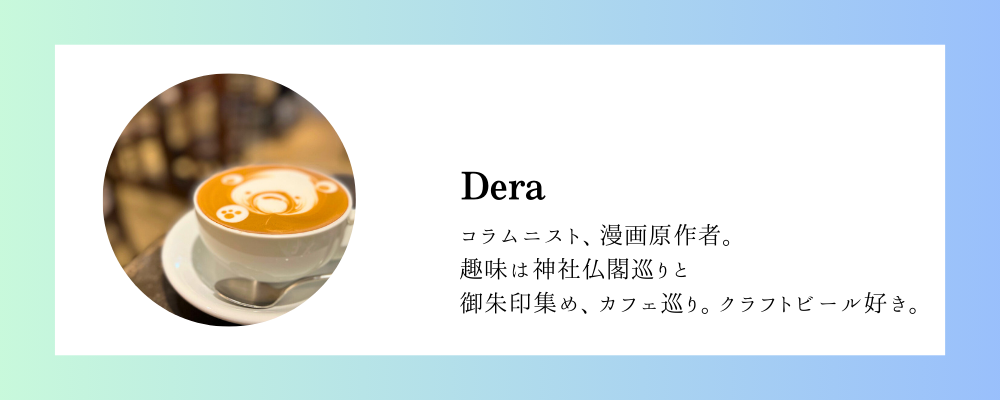
気になるコラムや新しい記事をいち早くチェックできるので、ぜひ友だち登録してお楽しみください✨
空間を浄化する大人気「天然パロサント香」や、
都内有名寺院でご祈祷をいただいた「おきよめしお」や「おきよめミスト」、あります!